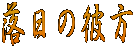
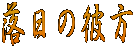
第11章 |
|
直実は混乱した。 その装束を見れば、少年が平家の名のある武将であることはわかる。この首を挙げれば功名は間違いないだろう。 そうするべきであるのは分かっているのに、直実にはすぐに斬ることが出来なかった。 以前の彼なら迷わず討ったであろう。今、それが出来ないのは、ひとえに彼の息子のことがあったからだ。 三草山で傷を負った小次郎は幸いにも命に別状はなかった。 とはいえ、彼が手傷を負った時の恐怖は言葉では言い表すことの出来ないものであった。合戦で命を落とすかもしれないと覚悟はしていた。それが武士の習いである。小次郎にも、幼い頃よりそう言い聞かせてきた。 けれど、現実に息子が危うくなった時、平静ではいられなかった。子を案じぬ父親が、果たしているだろうか。 そんな思いを味わったからこそ、この少年が命を落としたならば、この者の父がどれほど心に痛手を受けるか、分かる気がするのだ。 「……どうなさった、熊谷殿。早く、この首をとられるがいい」 少年はすでに死を受け入れていた。 その覚悟が哀しくて、直実は刀を持つ手を震わせる。 「いずこの公達であらせられるか。お名乗りくだされ」 「無用です。我が首を持って人にお聞きなさい。いずれ分かるはずです」 そうは言われても、太刀を持つ手の震えは止まらない。 「わしにもあなたと同じ年の頃のせがれがおります。せがれが怪我をしただけであれほどに辛かったのに、貴方が討たれたと知ったらどれほどかお父君がお嘆きでしょう。子を思う親の気持ちが、わしにはよく分かるのです……」 不意に、少年が瞳を上げた。 「御子息の具合は……それほどに重いのですか?」 「いえ、幸い浅手で済みました」 「そうですか……」 少年が微笑を浮かべるのを見て、直実は困惑した。その笑みが安堵から表れたものだとは、いくら直実でも分からない。ただ、その笑みがあまりのも澄んでいて哀しかった。 「……お立ち上がりくだされ。密かにお助けいたしましょう。さ、お早く!」 死なせてはならない。なぜか強くそう思った。 死ぬにはまだ早すぎる。直感かもしれないが、直実はそれに素直に従おうとした。 少年の細い腕を取り身体を起こさせる。立たせようとして、波に滲む血の赤さにギクリとなった。 それは彼の腹部から滴り、いまだ流れ続けて止まらない。あまりにも綺麗な赤すぎる色に、かなりの深手なのだと悟った。己がつけた傷だけに、直実は愕然となる。 彼の絶望が伝わったのか、穏やかに少年は笑った。 「お気づきだろう、この傷では長くはもたない。あなたの手柄だ」 「そんな……そんなつもりでは……」 「後は首を刎ねるだけ。簡単なことです」 淡々と告げる少年の言葉は、しかし直実には断罪されるようで辛かった。身を切られるような、という表現はこんな時に使うのだろうか。この時ほど、直実は自分が武士であることを悔やんだ事はなかった。 すでに取るべき方法が一つしかないとわかっていながら、直実は思い切れない様子であった。そんな彼を、敦盛は静かな眼差しで眺める。 本当に、心は穏やかだった。嵐の去った海のように。さざ波一つたたない。 小次郎の父に討たれる。因縁めいたものを感じるが、それこそが自分には相応しい罰なのかもしれない。小次郎を裏切った自分には。 脳裏には、ほんの数日前の一瞬の邂逅が再現される。小次郎の見開かれた目。自分を確かに見つめた彼の視線が忘れられない。 (もしかしたら、小次郎は裏切りなんて思っていないのかもしれない。それどころか、私のことなんて忘れ去っていたかもしれないな) それだけの存在でしかなかったのかも、と皮肉な思いが浮かぶ。裏切って、彼を傷つけてしまったと思っているのは自分だけなのかもしれない。己を卑下する自分に、情けなくて唾を吐きかけたい気持ちだった。それでも、今となっては自惚れることも出来ない。自分が、小次郎にとって特別な人間であった、と……思うのは願望に過ぎないとわかっているから。 ……いや、それすらも言い訳だ。 本当は、自分が彼を傷つけてしまったのだと、認めたくないのだ。だから、彼にとってそれほどの価値もなかったのだと、思い込みたいのだ。逃避、という言葉が浮かぶ。実際にその通りなのだろう。 それでも、あの時はああするしかなかったのだ。敦盛が割って入らなければ、忠盛は確実に命を落としていた。彼を助けたことに躊躇いはない。例え、その結果小次郎を傷つけてしまったのだとしても。後からどれほど後悔するかわかっていても。 (償いはしなければならない。私の命で、償うことができるとは思えないけど……) 小次郎の笑顔を思い出すと胸が痛くなる。多分、もう二度と見ることが出来ないからだろう。自分はあの笑顔を永遠に失ってしまったのだから……。 敦盛は懐から錦の袋を取り出した。『青葉』の入っている袋だ。自分の手が血に塗れていたので、錦の包みまで赤く染まってしまったが。 「……これを、ご子息にお渡し願えますか」 恐る恐る直実が錦の袋を受け取った。突然の願いに、今度こそ直実は訝しがった。 「何故、せがれに……?」 「それと、お伝え願いたい。小次郎殿に。この先も決してあの夕焼けを忘れない、と」 許して欲しい、というのは簡単だった。けれど、決して許しを請うことは出来ない。……許されるはずがないと、わかっているから。それだけのことを、自分はしてしまったのだから。 それでも。 これだけは伝えたいと、敦盛は願った。 「本当に……綺麗だった、と……」 全てを染めた茜色の光景。あの時にも言った台詞だ。真実を話せなくても、この思いだけは本当なのだと告げたくて。 あの時は伝わったと思う。けれど、今度はどうだろうか?もう、小次郎は自分の言葉など信じてくれないかもしれない。それでも。 ――――――もう一度、彼と、あの夕焼けを見たかった……。 「……あなたは、せがれをご存知なのか?」 名指しだったことが、ようやく直実にそう気づかせた。しかし、敦盛は答えなかった。 結局、敦盛は彼に対して名乗ることが出来なかった。自分は平家の敦盛だと、胸を張って名乗りたかったのに。誇りが持てるようにと頑張ったつもりだったが、何の成果も得られていない自分には、名乗る資格すらない。いずれ、この首が源氏の大将の元へと届けば、敦盛という名が小次郎にも届くだろうが、できるのならば自分から伝えたかったと思う。 ひづめの音が耳に届くと、敦盛は波の間に膝を付き、直実が首を落としやすいようにと前屈みの姿勢をとった。 「熊谷殿。さ、お早く。他の者に討たれる前に」 直実の瞳に涙が滲んだ。 それでも、彼は太刀を握りなおす。 「御免……!!」 一ノ谷の惨状は、二月七日の正午過ぎには全て終わっていた。 この日、平家は大敗し、多くの有力な武将を失う。 その中に。 無官太夫敦盛と、敦盛を見守ってきた彼の兄の皇后宮亮経正の名も連ねられていた。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
