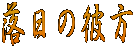
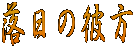
第12章 |
|
元暦二年(1185年)三月二十四日、壇ノ浦において平家は滅ぶ。 これにより、源平の争いに終止符が打たれることになり、以後、源頼朝は同族同士の争いに明け暮れることとなる。 小次郎は、武蔵の館裏の山道を、一人ぶらぶらと歩いていた。目的があるわけでもなく、何をしたいというわけでもないのだが、何となく、一人になりたかった。この山の中に分け入るのも久しぶりのことである。一時期は、全くここに寄り付かなかった。苦い思い出の為に無意識に避けていたのかもしれない。 それなのに、何故今になって来る気になったのか? それは小次郎自身にもわからなかった。 (時が経つにつれ、人の思いも風化してしまうからだろうか……?) そう考えて自問する。はたして、自分の思いは風化してしまったのだろうか? よくわからない、としか答えようがない。この1、2年はあまりに慌ただしすぎて、感慨にふける余裕もなかった。源平の争いの終わった今、ようやく心にゆとりが出来たのだから。 苦い思い出、といっても、この地にそれがあるわけではなかった。ここでの過去に暗いものなどない。ただ、ここには必ず付随する記憶がある。それが、小次郎に苦い思いを味合わせるのだ。 (三郎……) 父から彼が亡くなったと聞かされたが、小次郎に実感はなかった。義経の元に敦盛の首が届けられたそうだが、小次郎はそれを見ていない。望めば見ることは出来ただろうが、それを見ることは敦盛の死を認めてしまうことだと恐れ、出来なかったのだ。 それは、彼の死を認めたくないと、思っているからなのか? (憎んでいるんじゃなかったのか?この手で彼を討とうと本気で思っていたんだから。それなのに……俺は、三郎が死んだと思いたくないのか?) 己の心の動きがわからず煩悶する。 そんな小次郎の視界に、淡紅色の色彩が飛び込んできた。 「何だ?」 そこは木々が開け、草原となっていた。その緑の中に、ポツリポツリと淡紅色の花が見えている。よく見ると変わった形の花だ。花弁は4枚あるのだが、3枚は先端が尖った普通の形で三方を向いている。しかし、手前にある最後の1枚が袋状になっていて、上に向かって口を開いているのだ。 「“延命小袋(えんめいこぶくろ)”じゃないか。こんな所に生えていたのか」 山地や草原に咲く花で、決して珍しいわけではないが、何故か同じ地に何年も生えることはないという、不思議な花であった。 こうしてじっくりと眺めてみると、丸みを帯びた独特の花弁が母衣(ほろ)に見える。母衣とは、武者が矢を防ぐ為に背負った袋状の布のことだ。 まっすぐに伸びた茎の先に、一つの花しかつけない。 ――――――優しげでありながら、凛とした美しさをもつその姿に、小次郎は最後に見た敦盛の姿を重ねて思い浮かべた。 小次郎の懐には、敦盛から託された『青葉』がある。彼が何故、最期の時にこれを自分へ渡そうとしたのか、手渡された父もその理由を聞いていないという。 (これが、お前の心なのか……) 敦盛の全てに疑心暗鬼になった自分の元へと託された横笛。これが由緒ある名笛だとは聞かされていたが、あの時の自分にはそれはどうでもよいことであった。ただ、敦盛の美しい笛の音があれば、それだけで充分だったのだ。 (あの音色に嘘はないと、伝えたかったのか?お前は俺以上に苦しんでいたというのか?) 素性を隠していたことは、あの状況では当然だと小次郎も思った。それを彼にとっては都合のよいことだと解釈していたが、そうではなかったとしたら? あの優しい笑顔も楽しかった思い出も本当のことで、逆にそのことで敦盛が辛く思っていたのだとしたら? 騙された、と思っていた。 裏切られたのだと、憎く思ったのに。 「……裏切ったのは、俺の方じゃないか……」 敵として目の前に立った敦盛を見て、小次郎は即座に裏切りを信じた。懐かしい過去よりも、目の前の姿を信じた。――――――それはすなわち、敦盛本人を信じていなかった、ということなのだ。 彼を、責めることなんて出来ない……。 小次郎は苦しげに眉をひそめる。額を抑えて低く呻いた。 「三郎……」 ポタリと、雫が頬を滴り落ちる。泣いているのだと気づいたのはしばらく経ってからだった。 敦盛が死んでから、初めて流した涙だ。 鋭い刃物でえぐられているかのように胸が痛い。もう二度と彼に会えないのだと思うと、こんなにも心が苦しい。 憎むことなんて出来なかった。彼の死がこんなにも悲しいのに、もはや己の心を偽ることは出来なかった。生きていて欲しかった。例え敵同士で、もう二度と会うことが出来なくても、生きていてくれるだけでよかったのに。 ――――――もう、この世に彼はいないのだ。 嘆く小次郎は日暮れに気づいたのは、延命小袋が茜色に染まった頃だ。自分自身も赤く染まっているのだろうと、頬を濡らしながら空を仰ぐ。 稜線に沈む夕日は見えなくても、夕焼けの素晴らしさは伝わってきた。 『決してあの夕焼けを忘れない、本当に綺麗だった、と……敦盛殿が仰られていた』 直実が笛を渡しながら伝えてきた敦盛の最期の言葉。 彼の、心情を吐露した最期の……。 夕日の向こうに、敦盛の笑顔が浮かぶ。 「ああ……本当に、綺麗だな……三郎……」 小次郎は、敦盛へと笑いかけた。 延命小袋。 ラン科シプリペディウム属の多年草で、本州中部以北に分布している野生ランである。 古人はその丸みを帯びた独特の唇弁を母衣に見立て、源平合戦の哀話を重ねた。優しげでありながら儚さをも感じさせるその姿に、人は若くして散った敦盛への哀悼を託したのだろう。 ――――――現在、その花は“敦盛草”と呼ばれている。 |
|
| ←Back | |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
