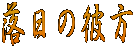
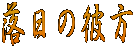
第10章 |
|
名を呼ばれたような気がして、小次郎は瞼を押し上げた。 見知らぬ天井に、ここが仮宿であるのだと知らされる。怪我をした為ここで静養しているのだと、遅まきながら思い出した。 意識が現実についていかない。ぼんやりとしている。まるで夢から覚めた感じで……。 夢を、見ていたのかもしれない。懐かしい武蔵の夢を。楽しかったあの日々を、夢の中で再現していたのかもしれない。 ……しかし、夢は辛い記憶をも蘇らせる。 (……三郎……) 小次郎は押し寄せる波のような過去の残像に、瞼をギュッと閉じた。 懐かしい武蔵の記憶から、もはや切り離せない光景となってしまっている彼と過ごした日々。ほんの数日前までは、茜色の夕焼けと共に何度思い出しても色褪せない記憶で、何度でも思い出したいと願っていたのに。 今は、思い出すのがこんなに辛い。 忘れられるものなら、全て忘れ去ってしまいたい。それが、できるのならば。 あのわずかな日々が、楽園にいるみたいに楽しかったのは否定できない。 否定できないからこそ、騙されていた自分が空しくなる。 (三郎は、平家の公達だった) (彼は、当然俺が源氏の者だということを知っていたはずだ) (知っていて、何も知らなかった俺を、嘲笑っていたんだ) 敵を目の前にしているのに、なんて呑気なのだろうと内心で呆れていたに違いない。何も疑おうとしなかった自分の馬鹿さ加減を笑っていたのだろう。 彼にしてみれば、運のよいことだったのだ。今だからこそ分かるが、あんな源氏の真っ只中で彼の素性が知れたら命はなかったに違いない。何も詮索しなかった自分はそんな三郎にとってはとても都合がよくて、怪我が治るまで利用したのだろうといまさら悟る。 ……結局は、全て自分が愚かだったのだ。 三郎のしたことは、平家の者なら当然のことで、人の好い自分が馬鹿だったのだ。あんなに簡単に信用して……裏切られて、当たり前なのだ。 それが分かっても、心の痛みは消えない。 三郎を信じていたからこそ、こんなにも自分は傷ついているのだ。女々しいと自覚していても心の傷を誤魔化すことは出来ない。肉体の苦痛ならば耐えることは容易い。けれど、心の痛みにはどうすればいいのだろう。 正しい答えかどうかは分からないが、小次郎にはその方法が分かっていた。 憎めばいいのだ。 騙されたのだから、彼を憎むことなど簡単だろう。憎悪を抱いて、報復を誓う。相手は平家で、討たなければならない敵だ。彼の首を討てば、この心の傷も癒されるのではないか。 (三郎を、憎む……) 「若殿、お目覚めになられましたでしょうか」 明かり障子に男の影が映っている。小次郎一人を置いていくのは心配と、直実が数人の下人を残していった。多分、若殿と呼ぶからにはその内の一人であろう。 なにやら彼の声が弾んでいる感じがして、小次郎は肩の傷を押さえながら身を起こした。 「どうした?」 「大殿よりの使者が参りました。一ノ谷での合戦、源氏の大勝に終わったと。さらに、多くの武将の首をあげ、義経殿御自ら労いのお言葉をおかけ下されたと!」 義経自らのお声掛かりとは、相当の手柄を立てたということだ。下人達が喜んでいるのも無理はない。 「父上はご無事か?」 「はい、すぐにこちらへ向かっているとのこと、いくらも待たずにお戻りなさるでしょう」 「そうか」 父の武勇を信じているとはいえ、やはり無事と聞くとホッとする。自分が手傷を負ったものだから尚更であった。 「あまたの首級の中には、かの平敦盛殿の首もあるとか。さすがは大殿でございます」 「敦盛殿……父上より聞いたことがある。相国入道殿の甥御殿だな」 直実は一時期平知盛に仕えていたこともある。父から平家の方々について話を聞いたことがある小次郎であった。 それから何刻も待たせず、父の直実がやって来た。 布団の上で正座をし、まずは父に祝いの言葉を述べた小次郎であるが。 意気揚々としていて当然であるのに、直実の表情は険しかった。息子の祝いの言葉にも、唇を引き結んで無言である。なにやら様子がおかしいと、小次郎の方も怪訝そうに眉をひそめた。 「父上……?」 「小次郎、お前……平敦盛殿を見知っておったのか!?」 敦盛とは先程下人の言葉にも出てきた名ではないか。直実がその首級を挙げたと聞いた。それなのに、何故こんなことを言い出すのか、小次郎には理解できなかった。 「一体、どうなされた……?」 不思議そうに見上げてくる息子の顔をじっと見つめると、何かに耐えがたくなったかのように直実は膝を付いた。そして、懐より細長い包みを取り出した。 錦の小袋で、一目でかなりの高価なものであると知れる。しかし、その美しい文様を赤黒いものが無様に汚していた。乾いた血がこびり付いている。 しかし、小次郎にはその包みが何なのか、何の意味があるのかわからない。 ゆっくりと包みを解く直実の指は震えている。 やがて現れた細長いものを見て――――――小次郎は瞠目した。 黒光りしているそれは、横笛であった。 小次郎の脳裏に光が瞬く。溢れ出す記憶。 確かに見覚えがあるもの……。 「……三郎の……?」 間違いなく、それは敦盛の『青葉』であった。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
