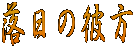
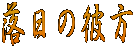
第3章 |
|
ある日、小次郎に請われて横笛を吹いたことがあった。三郎の荷物の中から目ざとく見つけていたらしい。 是非にとせがまれ、恥ずかしかったが三郎は笛を奏でた。 「綺麗な音色だな。すごいな」 高く澄んだ音色に聞き惚れていた小次郎が、嬉しそうに笑う。 「すごいって、この笛がいいものだからだよ。綺麗な音色を出すのは当たり前なんだから、私がすごいわけじゃないし」 謙遜ではなく、本当のことだと思っている。 笛の由来まではいえないが、由緒ある品で名笛である。これで綺麗な音を出せなければおかしいくらいだ。 しかし、それで納得する小次郎ではなかった。 「いくらすごい名器だからって、それを上手に使えなければいい音なんか出るわけないだろ?俺は楽のことには詳しくないけど、笛も三郎もすごいと思ったよ」 「あ、ありがとう」 真っ直ぐに見つめられて、三郎の方が照れてしまった。そんな風に言われたのは、初めてだったから。 この笛を奏でれば、必ず誉められた。 しかし、それはこの横笛が名器だから、または自分の家柄から、賞賛されていた。自分自身が認められたことなど一度も無かった。 妬む者だっている。彼らは、三郎が誉められるのは笛の為だと罵り、腕前を認めてはくれない。その通りだと、自分でも思ってはいたのだけれど。 嬉しかった。 小次郎は、自分という人間を認めてくれている。 何も知らないからこそ。 だが、それでも……嬉しかった。 「今度は俺の宝物を見せてやるよ」 笛の礼ということか、ニコニコと小次郎は立ち上がる。 何を持ってきてくれるのかと、期待した三郎であったが……。 ふわりと、宙に浮く感覚。 気づけば、三郎は小次郎の両腕の中に軽々と抱え上げられていた。 「な、な、な、な、何!?」 慌てふためく三郎を面白そうに見下ろす小次郎は、構わずに彼を腕に抱えたまま、館を飛び出した。 「今から行けば丁度いい時刻だから」 何が丁度いい時間なのか、問うても笑うだけで答えようとはしない。驚かせようという魂胆なのか。 全くわけがわからず慌てている三郎を腕に抱いて、小次郎は馬を駆けさせた。 どこへ行くつもりかと、口にのぼらせようとして三郎は止めてしまう。この様子では、何を質問しても答えてはくれないだろう。行き先に辿り着けばきっと全てがわかるのだからと諦めた。 (それにしても……何て上手に馬を操るのだろう……) 流れていく周囲の景色を見ると、明らかに二人は山中に分け入っていた。しかも、ちゃんとした道ではなく、どちらかといえば獣道のような所を。それなのに。 人間一人という大きな荷物を持って、しかしそんな重さを感じさせないような軽やかな馬術であった。こんなに上手く馬を乗りこなせる者を見たことがなかった。何ら危うげな様子もなく駆けるのが、三郎には神業のように思われた。 京に生まれた三郎が知るはずもないことだが、関東の人間は馬術が巧みである。 特別に小次郎の腕前が良いわけではなく、この地に住む武士にしてみればこれ位は当然のことであったのだが。 関東は、土地が痩せている。 他の地に比べ農業などに適さぬ土地柄、他に生計をたてるものが必要であった。 それが、馬の生産。 当時、全国にあった馬の生産地の内、その3分の2を関東が占めていた。 馬を飼育する為には、馬を十分に操れなければならない。自然と、関東人は馬術が上手くなるのだった。 後に平家を滅ぼすことになる源氏だが、彼らの強さの理由の一つは坂東武者の操馬術の巧みさであったとも言われている。 それを実際に体験したわけだが、今の三郎では馬術が戦の勝敗を決することになるとは思いもよらない。ただ、感心することしか彼には出来なかった。 そうして馬を駆けさせて。 どうやら目指す場所に辿り着いたらしい。小次郎は馬の歩みをゆっくりにさせ、山中を進んだ。 やがて。 視界が開ける。 そして、瞳が赤く染まった。 「わ、あ……」 三郎は、息を呑んだ。 その光景は、今まで見たことがないほど美しく、言葉を忘れさせてしまうほど心を奪われてしまった。 山々の尾根に沈みかけている、夕日。 夕焼けが空を、山を、三郎すら赤く……本当に赤く染めていた。 大自然の雄大な現象。人間など、ほんのちっぽけな存在としか思えぬほどに。 夕焼けを見たのは、これが初めてではない。京の都でだって、何度でも見た。 だが、これ程の感動を覚えたことがあっただろうか? 京で見た夕焼けと、この夕焼けの違いを言えと言われても、三郎には表現できない。その差異は、言葉にできるほど明確としたものではなかった。それでも、今までこんなに胸を打つような感動を味わったことはなかったのだ。 敢えて言うならば……強烈な色、だろうか。 ここまで鮮やかな茜色は三郎の記憶にはない。たかが太陽の光が、これほどまでに他者を染め上げるなど思いもしなかった。 本当に、現実のことなのだろうか……。 「……素晴らしいだろう」 小次郎の声を、どこか夢見ごこちで聞いている。 返答は出来なかったが、その通りだと思った。 「俺の一番大切なものだ。俺はこの国が好きだ。ここから見る光景が一番好きだ。この景色を、守りたいと思っている。その為なら、どんなことでもするだろう……」 命を捨てても構わない、と彼は告げた。 そうかもしれない。三郎だとて、この国で生まれたら、これが一番大切なものになっただろう。小次郎の気持ちはよく理解できた。本当に、それほどに素晴らしかったのだ。 だが……。 ここは、自分が生まれた国ではない。 皮肉にも、小次郎の台詞が三郎を現実に戻した。彼と自分との溝を、三郎に思い知らせたのだ。 生まれ故郷は、京だ。 例え他のどんな美しい土地を目にしようと、一番大切なのは、三郎にとっては都しかなかった。 小次郎は、源氏のものなのだ。 ここ数日の触れ合いがあまりにも楽しくて忘れかけていたが、彼とは敵同士なのだ。 感動を共有することは出来ても、根本はまるで違う。 決して、相容れることの出来ない価値観の差。 それでも。 「……本当に、綺麗だよ……」 小次郎の耳に届くように、呟いた。 真実を伝えることの出来ない彼に、しかしこの思いは本当なのだと伝えたくて。 せめて、この思いだけしか伝えられなくても。 いつか、彼の優しい瞳が敵意に染まる時が来ても、この思いだけは偽りではないと、覚えていてほしかったから。 それは、叶うはずのない望みではあったが、心から三郎は願った。 願うことしか、出来なかった……。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
