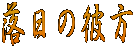
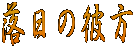
第2章 |
|
時は華やかなりし平安末期――――――源平合戦の頃。 鎌倉で清和源氏の嫡流・源頼朝が挙兵し、京の都を本拠地とする桓武平家の一族との戦を起こした。 平家が権力を握ることとなった保元・平治の乱の遺恨が発端ではあるが、頼朝の最終目的は父・兄弟の仇である平家討伐ではなく、武家による武家の為の政権……いわゆる、朝廷とは別の新たなる権力を作ることであった。 それは、決して平家の棟梁・清盛の権力の持ち方と同じではない。彼は朝廷と深く結びつくことで力を得た。 そうではなくて、頼朝は、朝廷と離れることで全く別の力を誕生させようと試みているのだ。 けれど、それは簡単なことではない。平家を倒せばそれが可能かといえば、否と答えるしかないだろう。 頼朝挙兵当時、日本は当の頼朝を入れて四つの勢力に分けられていた。西日本を清盛率いる平家、関東一円を頼朝が支配し、さらに、信濃以北に木曾義中が、東北に藤原秀衡がいた。 そして……後年、頼朝をして『日本一の大天狗』と言わしめた、後白河法皇のいる朝廷がある。 それらを全て平らげねば、頼朝の野望は決して叶うものではなかったのだ。 ともかく、まずは仇敵平家を討つことを念頭において、頼朝率いる源軍は戦いを仕掛けた。 そんな争いの中。 1181年閏2月、平清盛が没す。 強大な指導者のいなくなった平家に動揺が走った。 次の棟梁・宗盛は、清盛の子とは思えぬほど愚鈍な男で、誰もが彼に眉をひそめた。 けれど、平家の存続がかかっている戦で負けるわけには行かず、一族の結束を固めることに力を入れるのだった……。 小次郎の家は結構有力な家柄らしい。 まず、彼の館は、豪華さから言えば都の物には劣るけれども、関東らしいしっかりとした造りであった。下野の佐竹の館と同じ規模であったので、少なくとも彼と同等ぐらいの家柄なのだろう。 そして、使用人が大勢いるが、小次郎は彼らから『若殿』と呼ばれていた。 つまりは、この家の次期当主ということだ。 意外なところで意外な大物と出会ってしまい、三郎は肝を冷やす。もし、これで自分が平家の者だと知られたら……考えるのが怖くなってしまった。 しかし、小次郎本人には敵だと思わせるものが何もなかった。 もちろん、自分の身分を知らせていないことも理由の一つではあるだろうが、何よりも、彼自身の人柄が奔放で屈託がなく、純粋さを感じさせるからだろう。不思議と、彼の前では構えることも忘れてしまうのだった。 素朴さと純粋さは、地方ならではの特色なのだろうか。都では、彼のような人間にはお目にかかったこともない。何となく、貴重な存在に思えてしまう。 時折使用人達がこそこそと噂話をしているが、それも小次郎という人間を如実に語っていた。 「若殿は、また拾い物をしてきたって?」 「今度は何?犬かい?それとも猫?この間は山から猿も連れてきたよね」 「今度は人だよ。倒れていたのを見つけたんだとさ」 「とうとう人間まで拾ってくるようになったか。でも、若殿らしいな」 もちろん彼らの主人のいない所での会話だが、その仲には楽しげな笑い声も含まれている。慕われているのだと、強く伝わってきた。 (……しかし、犬や猫や、はては猿と同等に見られているのだろうか……?) 少し、情けなくなってしまう。 何よりも驚いたのは、なんと彼が自分と同い年だったということだ。 「……ということは、君って14歳、なの?」 「そう見えないか?」 「全然見えない……」 彼と比べたら、自分の体型の何と貧弱なことだろう。小次郎よりも一回りは確実に小さかった。腕も細いし、色も白いし……何よりも、三郎は常に童顔と言われていた。大きな瞳はまるで女のようだと自分でも嫌っているのだが、それが確実に彼を年よりも若く見せているのだ。 果たして、この差はなんなのだろう? 都と坂東の違い、と一概に決め付けるには三郎は自分に自信がなかった。 もし、自分が坂東に生まれ育っていたならば、彼のようになっていたであろうか……?……とても、そうとは思えない。 また、小次郎の言った通り、三郎はしばらく高熱を発したのだが、何と『若殿』直々に夜通し看病してくれたのだ。 小次郎は、 「気にするな。こういう性分なんだ」 と軽く笑う。 しかし、夜中にいつ目が覚めても、彼が起きていて冷たく冷やした手拭を額に当ててくれていた。一睡だってしていないかもしれないのに。 「……小次郎って、実は動物なんかの世話をするのが好きだろう……?」 いつの間にか彼に対して砕けた言葉遣いをしていたが、全く違和感はなかった。小次郎の方も気づきもしていない。 「よく分かったな」 「……それは、わかるさ」 「まあ、こういう性分なのさ」 どうやらそれが小次郎の口癖なのだろう。今までも、きっと周りから口うるさく言われていたに違いないと思い、笑いがこみ上げてきた。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
