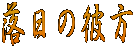
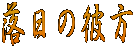
第4章 |
|
「……敦盛様」 寝具の中で眠りに引き込まれていた三郎は、囁くようなそれでいてはっきりと耳に届いた声に、ガバッと起き上がった。 「誰だ……!?」 「経盛様の手の者です」 「父上の……」 味方とわかり、ホッと息を吐く。 その男は部屋の隅に膝ま付いていた。いつ部屋に入ってきたのかわからないほど、気配というものを感じさせない男だった。 黒づくめの装束をしているのは、彼が訓練された者であることを窺わせる。 「随分とお探し申し上げました。まさか、源氏の館……それも、よりにも夜って熊谷の館にいるとは思いもせず、お迎えが遅れてしまい申し訳ありません」 「く、熊谷……あの武蔵の豪族の……!」 その名は聞いたことがあった。 一族を率いるのは、熊谷直実。 元来源氏の家人で、保元・平治の乱では源義朝(頼朝の父)に従い参戦したが、源氏が敗れると一族と共に平家の支配下に下った。 つい先ごろまで平知盛(清盛の次男)に仕えていて、頼朝が挙兵した先の石橋山の合戦では大庭景親と共に頼朝を敗走させたが、その後間もなくその廖下に属することとなった。 すると、小次郎はその熊谷の跡取なのか……予想通りの大物であるが、それでもショックは隠せなかった 「お父上がご心配なされております。急ぎ、戻られますように」 「で、でも……」 都に戻るのに戸惑いを感じるなんて、自分でも驚いてしまった。 戻る、と聞いて真っ先に浮かんだのは小次郎の笑顔。彼の優しさ。そして。 『こういう性分なんだよ』 照れたような微笑が目に焼きついて離れない。 今さらながら、自分の内で大きくなってしまった彼の存在に気づく。 「……っ」 やりきれなくて唇を噛み締めた。 彼の優しさは偽りの自分に向けられたものだと分かっていても、本当に嬉しかったのだ。 自分を自分のままとして認めてくれた彼だから……出来るのならば、友と呼びたかったのに。 ……友達にも、なれない。 もう二度と、あの笑顔を見ることが出来ない。 それがとても悲しくて、とても辛くて、そして悔しくて。 涙が零れそうだった。 そんな三郎を見つめて、男は躊躇いながらも言葉を紡ぐ。 「猶予はございません。木曾の源義仲の兵が都へ向かっています。食い止めることが出来なければ、都を捨てることも棟梁は考えておられるようなのです」 「都を捨てる!?」 馬鹿な、と吐き捨てる。 棟梁とは、前述した平宗盛のことだ。そんな馬鹿げたことを、彼が考えているというのか。 (今日こそが我等平家の地。その都を捨てて、一体何になるというんだ!) 「……分かった。すぐに戻る!」 足の腫れは大分引いたとはいえ、まだ満足に一人では歩けない。傷が治るまでいろと言ってくれた小次郎に対し、申し訳なさが募る。 それでも。 行かなければならない。自分は平家の一族なのだから。 二度と会うことはないかもしれない。 でも、その方がいい。 もし会うことが出来たとしても、今度こそは敵同士として対峙することになるだろうから。 その日が来なければいいと思う。 偽ったままの自分。許しを請うことも出来ない。 この胸の苦しさは小次郎に対する罪悪感だろう。彼に対する裏切りとさえ、思えてしまう。 (許してくれなくてもいい。罵られようと蔑まれようと構わない。でも、あの夕焼けだけは絶対に忘れないから) それだけを、己の誓いとして。 それだけしか、誓えなくて……。 ―――――――平敦盛。 平清盛の弟経盛の第3子。つまりは、清盛にとっては甥にあたる。 従五位下の位を持っていたが、官職がなかったので「無官大夫」と呼ばれていた。 横笛をたしなみ、鳥羽院から祖父忠盛に下賜された名笛『青葉』を譲られて、どこへ行くにも肌身離さず持ち歩いていたという。 まだ少年である彼は、しかし一族の為に奔走していた。 例え年若くとも、平家であるという自負があった。一族を愛し、その為ならば命を賭けても構わなかったのだ。 しかし。 落日はゆっくりと、しかし確実に間近まで迫ってきていた―――――― |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
