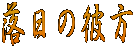
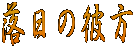
第7章 |
|
仲違いをしている源頼朝と木曾義仲は、平家の目論見を切って捨てるように和平を結んだ。 義仲の嫡男義高を、頼朝の娘・大姫の婿とすることで、血縁関係を深め共に平家を敵とすることを約したのである。 そして、義仲は京を目指す。 それを迎え撃つ平家だが。 木曾義仲との戦いは、平家が敗北を喫した。 寿永二年四月、燧城で義仲の前線の砦を突破したものの、その後倶梨伽羅峠・篠原では持ちこたえることが出来ず惨敗したのだ。 そして、七月二十五日。 一族は安徳天皇を奉じて都を後にし、西国へと逃れた。 ――――――いわゆる、平家の都落ちである。 一時は九州大宰府まで落ち延びたが、再び義仲が頼朝と争い合うこととなり、その隙に勢力を回復させた。 そして、福原京付近の一ノ谷に軍を移し、京都奪還の動きを見せ始めた。 それに対し、寿永三年一月に宇治川で義仲を破った源氏軍は、大手の大将として頼朝の弟・範頼が、搦め手の大将として同じく頼朝の弟・義経が軍を率いて一ノ谷へと向かった。 範頼の率いる五万六千余騎は西国街道を進んで敵の正面から、義経率いる二万余騎は丹波路から迂回して一ノ谷の背後から攻撃する作戦である。 源氏軍が定めた決戦の日は二月七日。 しかし、その三日前の二月四日の夜に、一ノ谷の前哨戦となる戦端が開かれる。 三草山の合戦である。 一ノ谷の背後に回ろうとした義経軍が、三草山に布陣していた平資盛ら率いる平家軍七千余騎と遭遇したのであった。 暗闇の中では戦が出来ぬと源氏軍は付近の民家をはじめ一帯の山野に火を放ち、赤々と燃え盛る炎を明かりとして一気に平家の陣へと突入して行った。 その中に、熊谷親子の姿もあった。 熊谷小次郎直家は、節縄目の鎧(白・浅黄・紺の三色の筋のある染革を細かく切ったもので縅した鎧)を来て、西樓という白月毛の馬に乗っていた。 彼にとってはこれが初陣である。 ところが、小次郎の威武堂々とした態度はとてもそうとは思えぬ雰囲気を感じさせていた。元々年齢より大人びているところがあったが、その様子はいたく彼の父を満足させた。さすがは熊谷直実の子よと、皆の賞賛を浴びているからだ。 当の本人は、周りの評価など歯牙にもかけていなかった。彼はいつも通りに振舞っているに過ぎない。周囲の期待が大きく膨らんでいるのを察してはいたが、彼自身はそれに圧されることも気負うこともなく、泰然と過ごしていた。 戦乱の最中にあってもそれは変わりない。小次郎は太刀をその手に握り、一人、また一人と敵を切り伏せていった。 敵の本陣に突っ込んでいく。彼の内には戦に対する恐怖というものがなかった。物心付く頃からそのように育てられている。例え自分の命が危うくなろうとも、決して取り乱すことはないだろうと小次郎自身も思っているくらいだ。 だからこそ、危険な先陣であろうとも、真っ先に飛び込んでいく武勇を見せた。 「小次郎!敵の大将は平資盛殿。副将は有盛殿、師盛殿、忠房殿だ。必ず首を取れ!!」 父の叱咤を背に受け、敵将目指していく。 平資盛・有森・師盛・忠房は兄弟であり、清盛の孫である。彼らの首を討ち取れば、功名になるのは間違いなかった。 敵将と思しき人物を見つけて切りかかる。 相手も負けじと刀で受け止めた。そうして敵の顔を覗き込んで、あまりの幼さに小次郎は胸を突かれた。 自分もまだ子供であるとは思っているが、それよりもなお若い。多分、12〜13歳位だろう。周りの声からこの少年が平中房だと知った。 不意に、小次郎は約一年半前に行き倒れていた少年のことを思い出した。 三郎という名以外素性は知らない。 ただ、とても澄んだ瞳の持ち主だったという記憶がある。 あの頃の彼もこの目の前の少年位の年齢だっただろう。現在はもっと成長しているとは思うが、彼の内では年齢以上に幼い顔立ちをした三郎しか思い浮かばない。 彼と過ごしたのは一ヶ月にも満たなかったと思う。 何も言わずに、突然姿を消した少年。 笛の音が、とても綺麗だった。それは鮮明に思い出すことが出来る。あんなに綺麗な音色を聞いたのは生まれて初めてで、とても感動したのだ。 そして、自分の宝物を見せた。 親にさえ内緒にしていたあの風景。茜色の夕焼けを、彼は声もなく魅入っていた。自分と同じ感動を彼も感じてくれたのだと嬉しかった。 黙っていなくなってしまってかなり落胆した。もっと色々なことを話し合いたかったのに。あの少年といて、とても楽しかったのに。 別れの言葉の一つもなかったことを恨めしく思う気持ちも少しだけあった。 しかし、それよりも足の怪我はどうなったのだろうと心配した気持ちの方が強かった。 その後会うことも出来るだろうと期待したこともあった。結局は、再会できはしなかったけれど。 今、彼はどうしているだろう。 忠房に切りかかる手は休めずに、小次郎は思いを馳せた。彼の心を父親が読めたら、戦の最中に何を考えている、と怒ったことだろう。 それでも。 忠房の幼さは、彼に三郎を鮮明に思い出させたのだ。 「くそっ……!」 罵声を吐き、忠房は息を乱す。彼は小次郎に圧されていた。 ただでさえまだ成長しきっていない肉体に、慣れない立ち合い。すでに彼の身体の方が悲鳴を上げているのだ。 握力もなくなってきて、とうとう忠房は太刀を払い飛ばされてしまった。 素手になってしまった忠房の首筋に、狙いを定めて小次郎は切っ先を振り下ろす。 まだほんの少年ではあっても、これは戦なのだ。少年の方も武士であるのだからその覚悟は出来ているはず。 彼を哀れむ気持ちはあったが、迷いなく討つつもりだった。 「忠房殿、お覚悟!!」 忠房の顔が、恐怖に歪む。 忠房の首筋に食い込むはずの刃は――――――寸前で、止められた。 「なっ……!?」 今回の出陣で、およそ感情の起伏が見られなかった小次郎だが、初めて彼は驚愕の声をあげた。 彼の太刀は、横合いから割って入った太刀によって受け止められていた。 敵将の首をあげる一太刀を、止められたことも驚くべきことだった。しかし。 小次郎を愕然とさせたのは。 ――――――刀の切っ先を受け止めた人物を、見たからだった。 「まさか、そんな……」 小次郎の驚きに構わず、その人物は彼の刀を思い切り振り払った。 とっさに踏みとどまるも、衝撃から立ち直れていない小次郎は臨戦状態にはなっておらず、その隙を突かれて右肩に敵の一撃を受けてしまった。 「小次郎!?」 どこかで父の呼び声が聞こえる。 しかし、その声はとても遠く感じた。いや、今や小次郎にとっては周囲の戦乱さえも、別世界の出来事のようであった。現実から切り離されてしまったかのように、彼は全ての知覚を放棄してしまった。 正確には、目の前の人物以外を。 信じられない。こんなことがあっていいのだろうか。 思考が鈍い。現実を把握できない。 どうして……どうして、彼がここにいるのだ? 「……三郎……?」 血に濡れた太刀を構えて忠房を庇うように立つその姿は、思い出の中と変わらぬ容貌の敦盛であった。 変わっていないと、こんな時なのに呑気に考えてしまう自分は何なんだろう。右肩から溢れる血を押さえながら、これは夢ではないのだとようやく認識することが出来たのに。 本当に、変わっていない。 同い年だから16歳にはなっているだろうに、その大きな瞳も、丸みを帯びた頬の線も、小柄な身体も、記憶の中の敦盛そのままだった。強いて言うならば、少しだけ背が伸びただろうか。幼く見えることを嫌う彼だから、それはとても嬉しかっただろうな……と笑みさえ浮かんできそうだった。 敦盛は、萌黄匂の鎧を着ていた。ただし、兜は被ってはおらず、肩の半ばまで流れる細糸のような髪をなびかせている。 彼の目はまっすぐに小次郎に向けられていた。唇を引き締め、険しい表情をしている。 目を逸らすことなく、彼は背後の忠房に声を掛けた。 「忠房、退くぞ」 「で、でも……敦……」 「もうここは持ちこたえられないんだ!」 忠房の呼びかけを遮って、無理矢理彼の背を押して下がらせた。 小次郎は、身動き一つ出来ず、敦盛が平家の軍勢をまとめて戦場を離れるのを見ていた。 一度だけ、敦盛は振り返って小次郎を見た。その瞳が今にも泣き出しそうに見えたのは、小次郎の目の錯覚だろうか。 平家軍が逃走すると、激しかった混乱も収まってくる。 ようやく父の直実が駆け寄ってきた。 「小次郎、大丈夫か!?」 自分を抱える腕に、右肩の傷が激しく痛み出す。 いや、ずっと痛みはあったが、感覚として受け止めてはいなかった。ようやく、夢から覚めたような感じなのだ。 夢ならば、良かったのに。 薄れゆく意識の中で、小次郎はそう思う。 何も言わずに姿を消した彼。 ――――――自分は、騙されていたのだ…………。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
