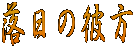
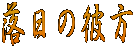
第6章 |
|
「ご無事でお戻りくださりよかったです」 敦盛は長兄の経正と肩を並べて、大内裏を出るべく朱雀門に歩を進めていた。 通盛は、折角の兄弟の再会に水を差すことは出来ないと、気を利かせて先に姿を消した。 気を使わせて悪いとは思ったが、反面ありがたくも思ってしまう。隣を歩く、自分より頭二つ分はゆうに大きい長兄は、敦盛にとっては自慢の兄だった。 皇太后亮兼丹後守である経正は、琵琶の名手としても有名で、名器『青山』の持ち主でもあった。武勇にも優れ、文武両道というのはまさにこの人のことであろうと、敦盛は思っている。 一時は自分も命の覚悟をした位だ。再びお互い無事に会うことが出来て、本当に嬉しかった。 しかし、対照的に経正は表情を曇らせる。 「……あまり、良いことはないのだがな……」 「……兄上?」 「……多くの兵が命を落とした。責は、軍を率いていた私にあるのに、それなのに私は無傷で、敗軍の将としておめおめと戻って来てしまった……」 何百何千という人命が失われた。自分の采配がもっと上手ければ、そんなにも死なせることはなかっただろうに。一軍の将としての重圧感と責任感が、経正の肩には重い。自分の才の無さを、悔やむことしか彼には出来なかった。 経正の苦悩は、聡い敦盛とは言えども理解することは難しかった。対象としての重圧を背負ったことは無いのだから。こんな時、苦しむ兄にどんな言葉をかければよいのかわからない。 だから。 その胸の想いを、正直に伝えることしか出来なかった。 「それでも……私は兄上が無事で、本当に嬉しいです。会うことが出来て……もう会えないかもと思っていたから……」 溢れる思いをどう表せばよいかわからず、言葉を詰まらせる。 それでも、経正は初めて笑みを浮かべた。 「そうだな……。私もお前のことをずっと心配していたよ。お前が無事で……良かった」 逆に、敦盛の表情が強張る。 無事だったのは、小次郎がいてくれたおかげだ。 彼に助けられなければ、馬も無く怪我した足で生き延びられたとは思えない。 小次郎の、優しさのおかげなのだ……。 沈み込んでしまった愛しい弟を、慌てたように覗き込む経正。 「敦盛?」 「……命の恩人がいるのです。彼がいなければ京に戻ってくることは出来なかったでしょう……」 大きな恩を受けた彼を、何より、ずっと親しくしたいと思った彼を。 騙したまま。 何も言わずに置き去りにした。本当に大切に思うのならば、誠実であらねばならなかったのに。 それなのに、自分は……。 俯き肩を震わせている敦盛の姿は、まるで泣いているように見えた。実際に涙を流してはいなかったのだが、それ程に今の彼は傷ついているように見えたのだ。 関東への潜入で、敦盛に何があったのか。彼自身の口が語らねば、どんな出来事があったのかは経正にはわからない。 「……敦盛……?」 「……私はずるい……彼はあんなにも真摯な態度で接してくれたのに、私は本当のことは何も言わず偽ってばかりで……。こんな私が、彼と友になりたいなんて言ってはいけないのに……。だけど、私は……」 「――――――お前だけが悪いわけではないだろう。事情はわからないが、お前は十分に苦しみ傷ついている。それ以上自分を責めるのはよしなさい……」 敗北に対する自責の念が誰よりも強い自分が言えることではないのだけれど。 自嘲しながら、それでも頭を振る弟を胸に抱きとめる。 これ以上、彼が苦しむ姿を見たくはなかった。 『彼』というのが誰なのか。何故、敦盛がそれ程に自分を責めなければならないのか、察することも出来なかったが、それでも弟が自分を許せずに責め抜いているのを見るのは辛いことであった。 経正の優しく背をさする手の温もりを感じて、けれど、敦盛にとってそれは何の慰めにもならなかった。 確かに、こんなにも苦しい。 自分の罪悪を分かっているからこそ、余計に辛い。 けれど、それが免罪符になるというのか。 苦しんでいれば、何をしても許されるのか。 そんなことは無いと心のどこかで声がする。言い訳にすらならない。 騙している自分より、騙されている方が何倍も傷つくことは、誰でも分かることだ。 自分を責めても何にもならないことも分かっている。それでも……自分自身が許せなかった。 そうするしか、選ぶ道は無かったとしても。 小次郎の優しさを、踏みにじった。 何も言わずに……別れの言葉すら残さずに、武蔵を出てきた。それ以来、ずっと敦盛の心を占めるのは、楽しかった小次郎との思い出であった。 忘れたことなど、無かった。 そして。 何も言うことの出来なかった己の立場を振り返り、諦めの嘆息をする。結局、二人は源氏と平家。相容れることは出来ない。価値観が違いすぎる。それは、あのわずか数日の日々で嫌というほど思い知らされた。同じ武士であるのにどうしてこんなにも違うのだろうか。いっそ、不思議にさえ思えてしまう。 何故……分かり合えないのだろうか。 源氏と平家に、どれほどの差があるというのだろう。 この時の敦盛は、それをわかっていなかった。だからこそ、こんなにも苦しんでいるのだろう。源氏と平家の違いが理解出来ていれば、割り切ることも出来たのだろうに。 けれども、その現実を敦盛はすぐに、本当にすぐに知ることとなった。 「父上の仇!」 甲高い、どこか幼ささえ残る声が響き渡り、敦盛と経正は目を瞠った。 煌めく白刃が視界に入り、反射的に身をかわす。 「……子供……?」 経正の呟きが耳に届く。 身体に不釣合いとも思える刀を掴んで睨みつけてくるのは、わずか7〜8歳としか見えぬ幼子であった。小さな身体、小さな手に、重そうに抜き身の太刀を構えて。しかし、その瞳は強い決意に燃えている。 憎悪。 こんな小さな子供がどうしてこんな感情を覚えるのか。自分達を襲った理由よりも、敦盛にはその方が不思議に思えてしまった。 身なりは、それ程貧しくは無い。中流か下流貴族の息子ではないだろうか。桜色の水干姿は、こんなにも可愛らしいのに。 子供の闘志は消えてはおらず、狙いを経正へと絞ったようだ。敦盛には目もくれず、経正に向かって何度も刀を突き出そうとする。 もちろん、こんな小さな子が大きな刀を振り回すのだから、動き自体はとても鈍い。経正は危なげなく避ける。しかし、それからどうしたものかと悩み、手を出しあぐねていた。 見かねた敦盛が、止めに入る。 「やめなさい!」 背後から羽交い絞めにする。放せと叫んで手足をばたつかせるが、いくら非力の敦盛でも子供の抵抗なら封じることが出来た。 騒ぎを聞きつけ、朱雀門を守る衛士が数人駆け寄ってきた。気づけば、門はすぐ近くのようだった。 「どうなさいましたか!?」 「この子がいきなり切りつけてきたのだが……」 困惑した表情で経正は子供を見下ろした。 襲い掛かられた理由が経正兄弟には分からない。父の仇と叫んだが、とんと覚えのないことであった。 「あ、この子は……」 衛士の一人が、子供の顔に見覚えがあったのか、哀れむような顔になる。 「知っているのか?」 「先頃まで清宗殿(平宗盛の長子)の守り役をしていた者のご子息です」 それを聞いて、今度は経正があっと声を上げた。 「兄上?」 「……確かに、父の仇だな……」 深い溜息を吐きながら経正が説明をする。このものの父は、実は先日処刑されてしまったのだと。 「……どうしてですか?」 「清宗殿がお忍びで市井に出られたことがあってな、友はその子の父親のみであったのだが、盗人に襲われて……深手を負いながらも賊を撃退したが、清宗殿に小さな掠り傷を負わせてしまった。ご子息に傷を負わせたことを宗盛殿が酷くお怒りになり……と、私も人から聞いた話だが」 「何てことを……」 酷い話に、思わず敦盛の手が緩む。 その隙に、子供は彼の手を振り払った。その際、ガリッと音がして、子供の爪が敦盛の右頬に引っかき傷を作る。 鈍い痛みが走り、目を眇めて子供を見た。 彼は、その大きな瞳に涙を一杯にためて、それでも気丈に敦盛を睨みつけていた。 「父上が何をしたって言うんだ!悪いことは何もしていないじゃないか!悪いのはお前達平家だろう!」 「な……」 「父上を返せ!!」 激情に駆られたのか、大粒の涙が零れ落ちる。 胸が痛んで声が出ない敦盛に、子供は地面に落ちている自分の拳大の石を拾い上げると、思い切り敦盛に向かって投げつけた。 石は、敦盛の額に当たる。 あまりのことにとっさに動くこととも出来なかった衛士達だが、子供が身を翻して逃げようとすると、はっとしたように刀を抜いた。 「何てことをするんだ!平家の若様だぞ!!」 いくら子供でも、許されることとそうでないことがある。衛士達は、役目柄子供を捕まえようと追いかける。 しかし。 「追うな!」 厳しい声が、彼らの足を止めた。 制止の声を発したのは、額から流れる血を拭う敦盛自身であった。 「……追わないでくれ……」 「敦盛……」 子供の姿はもう見えない。 それなのに、敦盛の脳裏には、彼の憎悪に燃える瞳が焼きついたように離れなかった。 憎しみが、こんなにも激しい感情だということを、初めて知った敦盛であった。 そう、初めて……。 「……我々は……こんなにも憎まれていたのですね……」 ズキズキと痛む傷を押さえて俯く弟に、経正は何も言わなかった。言えなかったのだ。 真実だから。 平家は憎まれている。権力者の奢りが、皆の憎悪を買っている。だからこそ、源氏の元へと走る輩のなんと多いことか。 (小次郎も、そうなのだろうか?彼も、平家を憎んでいる……?) 憎まれていたのだろうか。 小次郎に。 自分の愛する平家は。 愛しているからといって、決して正しいわけではないことを、ようやく敦盛は理解することが出来た。いや、もしかしたら間違っているのかもしれない。だからこそ、源氏とは敵対しているのだろう。 友になりたいと、思うことこそが間違っているのだと、敦盛は打ちのめされた。 願いは決して叶うことが無いと最初から分かっていれば、こんなにも辛くは無かったのだろうに。 出会ったことすら後悔してしまう。どうして、彼はあの時自分を助けたのだろう。あのまま放っておいてくれた方が、いっそ良かったとさえ思えてしまう。例え、それで自分は死んでいようとも……そこまで考えて、自嘲する。 死ねば悲しむ人がいるとわかっているのだから、その例えは無意味だ。 あの時の自分は、決して生を諦めることはなかっただろう。父との約束を、何があろうとも守ろうとしたに違いない。 そして、小次郎ならば、あのような状況で見捨てるような真似はしまい。 本当に人が好い男だから。 結局は……なるべくしてなったという感じがする。 出会いも別れも、初めから定められていたかのように。 それならば。 「……兄上」 「何だ?」 「兄上は……もし生をやり直すことが出来るとしたら、再び平家の一族であることを選びますか?」 問いかけの意図が分からず、経正は首を傾げる。 敦盛の声は笑いを含まず、唇の端が震えてさえいた。 それを感じ、経正は真剣に考えた。誤魔化しや飾りではなく、本当の経正の気持ちを知りたいと考えてのことだと思ったからだ。 「そうだな……はっきりと言ってしまえば、平家であるということは今ではそう誇れることではないだろう。それでも、私は平家である自分に誇りを持ちたいと思っている。何度やり直そうとも、同じ道を選ぶだろう」 兄の答えには、迷いや躊躇が全く含まれていなかった。 彼がそう答えることは、敦盛にも分かりきっていたことである。 それでも、今はその答えが切実に聞きたかったのだ。 (私も、何度生まれ変わろうと、平家である自分を選ぶだろう) 奇妙な確信。やはり自分は平家を愛している。 一族の為ならば、きっと死すら厭わず戦うだろう。 だから。 どこまでも小次郎とは敵対することになる。 それが運命なのだと、ようやく敦盛は納得することが出来た。 それは、とても悲しいことであったのだけれども……。 ――――――二人で見た夕焼けが、胸に蘇った。 |
|
| ←Back | →Next |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
